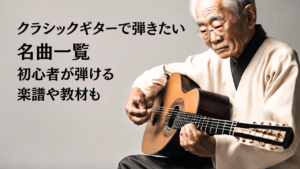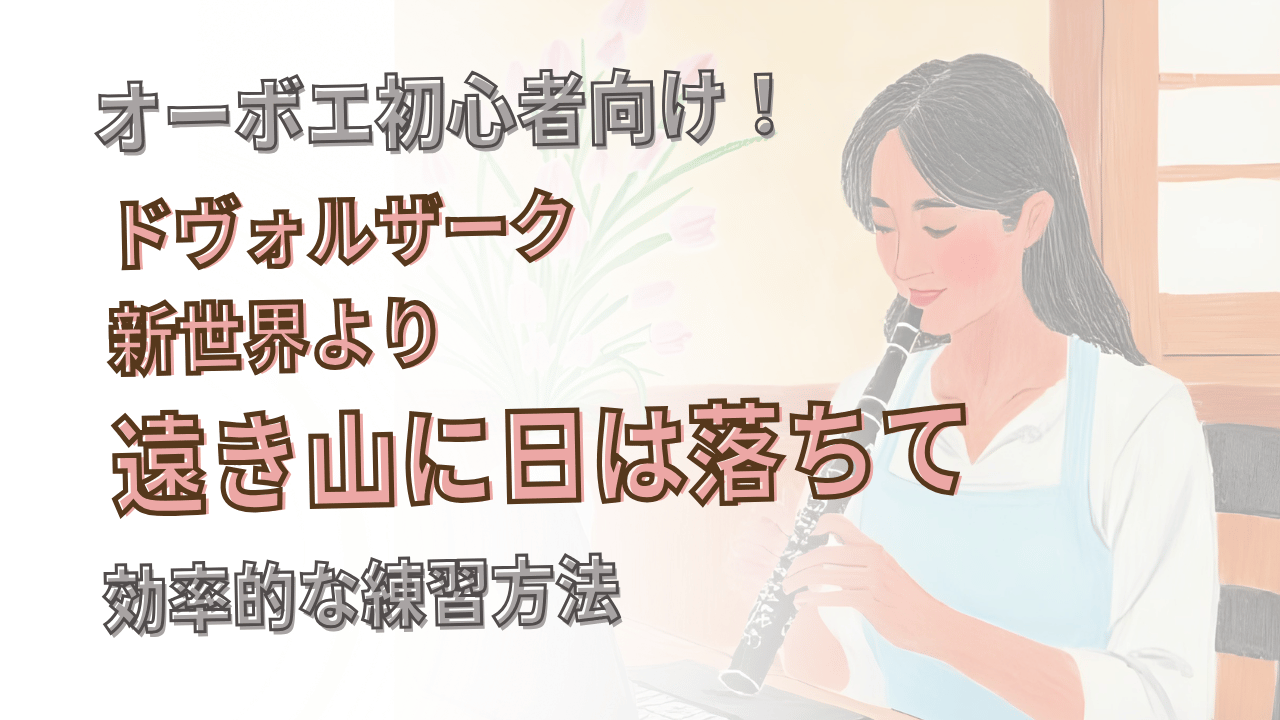
夕暮れ時にふと口ずさみたくなるような、哀愁と温かさをあわせ持ったメロディ――それが「遠き山に日は落ちて」です。この曲は、アメリカの作曲家デンツァが作曲した「家路(Going Home)」を原曲とし、ドヴォルザークの交響曲第9番『新世界より』の第2楽章に旋律が登場することで知られています。日本ではNHKのラジオ番組『夕べのひととき』のテーマ曲として広まり、多くの人に愛される名旋律となりました。
このゆったりとした旋律は、オーボエの音色にぴったり合う一方で、初心者にとっては息の流れや音のつながりなど、意外と難しさもある一曲です。今回は、この「遠き山に日は落ちて」をオーボエで吹けるようになるためのポイントと練習方法を解説し、最後には佐藤先生のオーボエ講座を活用して効率的に学ぶ方法もご紹介します。
「遠き山に日は落ちて」はどんな曲?
「遠き山に日は落ちて」は、ゆっくりとしたテンポの中に広がりのある旋律が特徴で、静けさと深い情緒を感じさせる作品です。もともとはオーケストラで演奏される壮大なスケールを持つ旋律ですが、シンプルなメロディラインの中に、情感豊かな表現が求められます。
音域はそれほど広くなく、リズムも基本的には4分音符と2分音符が中心で構成されているため、オーボエ初心者が初めて“表現力”を意識して取り組むのに最適な曲と言えるでしょう。
遠き山に日は落ちてと「家路」の違い
遠き山に日は落ちてと家路(Going Home)は、どちらもドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」第2楽章の旋律をもとにしています。ただし、「遠き山に日は落ちて」はこの旋律に日本語の歌詞をつけた日本独自の唱歌であり、主に学校教育などで親しまれてきました。
一方、「家路」はアメリカの作詞家が英語詞をつけたもので、故郷への郷愁を歌う内容になっています。曲のメロディは同じですが、歌詞の内容や文化的背景に違いがあり、それぞれの国で異なる情感をもって受け入れられています。
| 項目 | 遠き山に日は落ちて | 家路(Going Home) |
|---|---|---|
| 言語 | 日本語 | 英語 |
| 歌詞の内容 | 夕暮れと静けさ、自然の情景 | 故郷への帰郷、安心と懐かしさ |
| 使用メロディ | 「新世界より」第2楽章の主旋律 | 同上 |
| 成立 | 日本の唱歌として戦前から定着 | 20世紀初頭にアメリカで誕生 |
| 主な使用場面 | 学校の音楽教育、卒業式など | 葬儀・追悼の場面、ポピュラーソングとして |
オーボエで演奏する際のポイント
この曲を演奏するうえでの最大のポイントは、**「音をつなげる技術」と「息のコントロール」**です。テンポがゆったりしているため、一音一音の鳴り方や音の終わり方が目立ちやすく、少しの息の乱れや不安定な音程でも違和感が生まれてしまいます。
特に注意すべき点は次の3つです。
音の入り方と抜き方を丁寧にすること。
一音のアタック(吹き始め)を柔らかく、押しすぎず、自然に鳴らすことが重要です。また、音の終わりをすっと切るのではなく、少し余韻を残すように抜くことで、フレーズがより滑らかに聞こえます。
息の長さと配分を考えること。
この曲はフレーズが長く、一息で吹ききる部分が多いため、呼吸のタイミングと息の量のバランスを考える必要があります。息が途中で尽きてしまうと、せっかくのメロディが不自然に途切れてしまいます。
音程の安定と音色の統一。
中音域を中心に構成されているこの曲では、音程のズレが目立ちやすくなります。特にC〜Eの音域で音が上ずったり、音色が細くならないように、アンブシュアと息の角度を調整しながら丁寧に吹くことが大切です。
「遠き山に日は落ちて」の実際の練習方法
練習の第一歩は、メロディをしっかり「歌う」ことです。曲の流れや抑揚を口ずさみながら覚えていくことで、自然と息の流れやフレーズの構成を体で感じられるようになります。
その後、譜面を見ながら2小節ごとに区切って練習していきましょう。テンポは♩=60程度から始め、正しい音程と指使いを意識しながらゆっくり吹きます。
この段階では、音の出だしと終わりを特に意識します。アタックが強すぎたり、音がブツ切れになっていないかを録音で確認すると効果的です。
さらに、フレーズ全体を通して吹く際には、ブレスの位置を事前に決めておくことが大切です。無計画に息継ぎをすると、フレーズの流れが乱れ、聞いている側も違和感を覚えてしまいます。
音が安定してきたら、ピアノ伴奏や音源に合わせて演奏してみるのも良い方法です。他の楽器とのアンサンブル感覚を持ちながら演奏することで、リズム感や間の取り方が自然と身についていきます。
「遠き山に日は落ちて」上達の近道は、上手なオーボエ演奏を見て真似ること!
ここまで、音の出し方や練習方法を解説してきましたが、オーボエは文章だけでは伝わりにくい繊細な楽器です。「どのくらいの力で吹けばいいの?」「音の終わりってどうやって消すの?」といった疑問は、実際に吹いている様子を“見て”“聴いて”学ぶことが一番の近道です。
そこでおすすめなのが、佐藤先生のオーボエ講座です。
この講座では、「遠き山に日は落ちて」のような初心者にも馴染みやすい曲を題材に、動画とテキストを連動させた分かりやすい指導が受けられます。フレーズごとの吹き方やブレスの位置、音のつなぎ方など、教本や文章だけではつかめない細かなポイントも、実演を見ながら自然と身につけることができます。
初めてオーボエに触れる方でも安心して学べる構成になっているので、独学に不安がある方にもぴったりです。

オーボエを演奏できるようになりたい、
上達させたい人に朗報です!
ずっと憧れていたオーボエ。でも独学では・・・
初めてでも、合奏で自信がない人も自宅で本格レッスンが可能なオーボエ教材です。
ペール・ギュント組曲より「朝」(グリーグ) / くるみ割り人形より「花のワルツ」(チャイコフスキー) / 惑星より「木星(ジュピター)」(ホルスト) / キラキラ星 / ヒンケNO.1 / 新世界より「遠き山に日は落ちて」(ドヴォルザーク) / G線上のアリア(バッハ) / バレエ組曲「白鳥」より「情景」(チャイコフスキー) / 交響曲第9番「グレート」より(シューベルト) / セレナーデ(シューベルト)
あなたの音で、夕暮れの情景を奏でてみよう
「遠き山に日は落ちて」は、技巧的な派手さはありませんが、音楽の心を伝える一曲です。丁寧に音を出し、フレーズをつなげていく中で、オーボエという楽器の本当の魅力に触れることができるでしょう。
その第一歩を、佐藤先生の講座とともに、確かなものにしませんか?
やさしいメロディの中に込められた静かな感動を、あなた自身の音で表現してみてください。
オーボエで上手に名曲を奏でられるようになりたいなら、
この練習方法が最も近道です!
「世界一難しい楽器」とギネスに認定されたオーボエの魅力に惹かれながらも、その難しさに挑戦を諦めてしまった音楽愛好家の皆様へ。これまで教材の不足が独学の壁となっていましたが、その壁を打ち破るために、初心者でも自宅で簡単に学べるオーボエ教材があります。この教材では、楽器の組み立て方から始まり、誰でも分かりやすい解説でオーボエの奏法をマスターできます。今こそ、オーボエの美しい音色を自分の手で奏でる喜びを体験してください。
上手になりたい曲があるならば、音楽教室に通うより断然お得!
さらに今だけ期間限定!